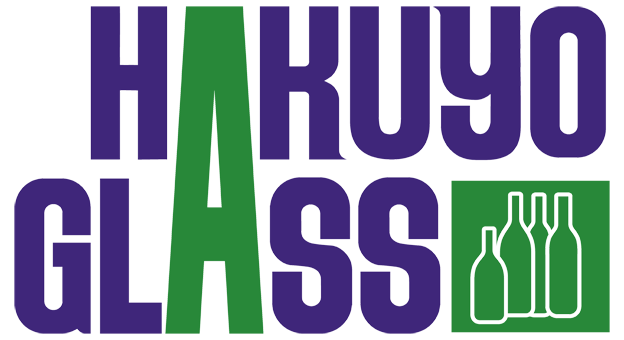柏洋通信
柏洋通信
2018.02.23
柏洋通信Vol.64
【ガラスびんフォーラム創立50年記念祝賀会が開催されました。】(2/23)
2月16日、ガラスびんフォーラムの創立50年を祝う祝賀会が、品川プリンスホテルで盛大に開催されました。
ガラスびんフォーラムとは、ガラスびん中小メーカーで構成する団体で、 1967年12月に全国自動壜工業会として、当社を含む9社で産声を上げました。
その後1990年3月に現在の名称に変更し、50年を経た現在は、 医薬品、食品、お酒、化粧品など、各社がそれぞれの得意分野で活躍する7社で構成されています。
その間1990年にガラスびんの生産量はピークを迎えますが、残念ながらその後市場ニーズやライフスタイルの変化に伴い、 ガラスびん需要はダウントレンドが続いていると言わざるを得ません。
それでもガラスびんの持つ安全性や高いリサイクル性、そして何より他の容器が持ちえない確かな存在観や高級感は、 多くの消費者に支持され続けています。
さて、当日は経済産業省をはじめ、多くの関係団体や日頃お世話になっている企業の皆様にお集まりいただき、 賑やか中にも和気あいあいとした雰囲気の祝賀会となりました。
ご来賓のご祝辞では、現在ホットな話題となっている、マイクロプラスチックによる海洋汚染に触れられたものもありました。
廃棄物となったプラスチックは完全に分解されることなく、微細な破片となって海中を漂い、 それらが食物連鎖の過程でより大きな魚に蓄積されていく現象が問題視されています。
ヨーロッパの一部では、樹脂容器のリサイクル率をもう一段引き上げる措置や、 課税を含む様々な規制を検討している国があるとか。
ガラスびんの持つ元々の特性は、一般消費者の間でも理解は進んでいると思いますが、 仮にガラスびんが海洋に廃棄物として投棄されたとしても、波間を漂う内に次第に細かく分解され、 最終的には無害な砂に変わっていくことは、意外に知られていない事実だと思います。
ガラスは割れるからこそ原料としてまた窯に戻るし、海の砂にも帰るのです。
これからは無理なく自然と同化できる容器が、新たな選択肢になるのでは。
そう考えると、何やらわくわくしてくるのは、ガラスびんメーカーの社長だけではないでしょう。
その後はテーブルを越え、グラスマン同士の歓談の輪が広がります。
そして、関根敏行トリオをバックに河埜亜弓さんの素晴らしいボーカルで、 祝賀会のボルテージは一気に最高潮に達しました。
大いに盛り上がりを見せた祝賀会も、いよいよ終わりの時が近づいてきました。
これまでの50年に感謝しつつこれからの50年に向け、ガラスびんフォーラムのみならず、 ガラスびんに関わる全ての団体、企業、そして関係者の方々の繁栄を祈念し、華やかに関東一本締めでお開きとなりました。
最後になりましたが祝賀会の開催に当たり、小西ガラスびんフォーラム会長をはじめ、 お手伝いいただきましたスタッフや事務局の皆様に、この場を借りて改めて御礼申し上げます。
七島 徹
2018.02.02
柏洋通信Vol.63
【みやぎ食品・飲料販路開拓展示商談会に行ってきました。】(2/2)
◆及川社長のお話では、東日本大震災で4つの工場のうち、3つが津波で流されてしまったそうです。ようやく再建に目処がつきつつあるとのことで、当社のガラスびんがお役に立てばうれしい限りです。
◆最近ガラスびんをリニューアルされ、新製品の「大葉のジェノベーゼ」を市場に投入。粟野代表、大ヒット期待しています!
◆トマトにとことんこだわるデリシャスファームの今野専務。新製品の「トマトジュレ」にモンブラン140を採用していただきました。
◆当日は多くのバイヤーが詰め掛け、地元テレビ局の取材も入っていました。別の開場では個別の商談会も行われていました。
◆三陸オーシャン様は海鞘(ほや)一筋。「独特の香り」が魅力の海鞘ですが、流通の方法が悪ければ、それが「臭い」に変わり敬遠されます。木村社長は本当の海鞘をもっと知ってもらいたいと、意欲的に取り組んでおられます。
◆(株)ファーマーズ・フォレスト松本社長。社長自らの実践に基づく貴重なお話に、多くの気づきをいただきました。
1月30日、宮城県仙台市のみやぎ産業交流センター(夢メッセみやぎ)で開催された、みやぎ食品・飲料販路開拓展示商談会に行ってきました。
このイベントは、宮城県内の農産・水産品と、それらを活用した加工食品や飲料の販路拡大を目的に、日本全国はもとより、 海外のマーケットをも見据えたビジネスマッチングの場として企画されたものです。
出展者はいずれもそれぞれの地元で頑張っている企業ですが、こうした機会に慣れていないところも多く、 海外への販路開拓にはジェトロが、国内の販路開拓には「フーデックス」で定評のある日本能率協会が全面的にサポートしています。
会場には80社以上が集まり、バイヤーたちとの商談にも熱が入ります。
当社の製品をお使いのお客様にも、しっかりご挨拶してきました。
商談でお忙しいところ、快くご対応いただきまして、この場を借りて、改めて御礼申し上げます。
同時に「食」に関するセミナーも開催され、当社のお客様でもある(株)ファーマーズ・フォレストの松本代表取締役が、講師として登壇されました。
松本さんは(株)ファーマーズ・フォレストの社長として、栃木県の道の駅「ロマンチック村」を中心に、地場の産品を活用した商品を幅広く展開されています。
当社もそうした中の一つである、クラフトビールでお世話になっています。
地域に根差した事業は物販に留まらず、こと消費を促すイベントの企画・運営や、全く新しい体験型旅行の提供など、我々の常識を遥かに超えて広がりを見せています。
松本さんはこうしたビジネスマンの顔を持つ一方、「農業と食、地域資源を結ぶ総合プロデューサー」として、地方を活性化するコンサルタントとしてもご活躍されています。
今回は「地方創生時代の集客方法や、稼ぐ仕組みづくりについて」のタイトルで、1時間超お話されました。
当社とは分野は異なるものの、幾つかのヒントをいただいと感じています。
「プロダクトインからマーケットイン」と言われて久しいですが、本当の顧客はだれなのか。
顧客の話は聞いているつもりでも、顧客の本当のニーズを掴んでいるのか。
松本さんのお話を伺いながら、当社の新製品開発の過程で、ここまで突き詰めてきたのか、自分たちの独りよがりになっていないか、改めて考えさせられました。
もう一つ、気になるエピソードを伺いました。
松本さんの会社では「大谷アンダーグラウンド」という体験型の旅行を企画していますが、大変好評だそうです。
栃木県の名産にかつて大谷石がありました。
現在は建築の志向も変わり、需要はすっかり落ちてしまいました。
石を切り出した現場は今や多くが廃坑と化し、地元ではすっかり負の遺産だと思われていました。
ところが、廃坑の奥深くに水が溜まり、まるで地底湖のような幻想的な風景が広がっていたのです。
これが新たな観光資源として蘇りました。
自社の持つ魅力や価値をきちんと理解し、活かしているのかを問われていると、「ハッとした」瞬間でした。
ここ「夢メッセみやぎ」では、新たなお客様との出会いと、柏洋硝子を見つめ直す貴重な機会をいただきました。
七島 徹
2018.01.26
柏洋通信Vol.62
【スマート工場EXPOに行ってきました。】(1/26)
東京ビッグサイトで1月17日から19日の日程で開催された、第二回スマート工場EXPOに行ってきました。
スマート工場とは、高度なファクトリーオートメーションに加えて、 工場内のあらゆる機器/設備 あるいは工場と工場を通信で常時つなげ、 IoT化することで生産革新を実現する次世代型の工場(主催者HPより)を意味することは、既にお馴染みです。
IoTやインダストリー4.0、AIなどの言葉は、テレビや新聞で目にしない日はないと言っても過言ではないでしょう。
ドイツやアメリカが先行し、日本でも大企業への具体的な導入例が続々と報道されています。
元々は製造業の生産性の向上を前提とした取り組みだと理解していたのですが、 今ではサービスや金融の世界での導入も進んでいるようです。
大企業はもとより、実は中小企業こそがIoTで劇的に変われるのだ、などと聞くにつけ、 最先端を行く工場で今何が起きているのか、何が起きようとしているのか、 自分の目で確かめなければならないという強い衝動にかられました。
また、当社の技術系の役職者にも参加を促し、係長以上全員がスマート工場の今と未来を体感してきました。
彼らにとっても大きな刺激になったと思います。
私は二日目の18日にビッグサイトを訪れました。
まず驚かされたのが会場の人の多さです。
高度な技術に特化した内容だけに、これほど動員力のある展示会は珍しいと感じました。
主催者側の発表によれば、同時開催のクルマやロボット関連までを含めると、11万人以上が集まったそうです。
事前に書籍やネットである程度勉強はしてきましたが、全体像を掴もうと出席したセミナー「AIとIoTが進化させるスマート工場の未来」では、 主催者側の予想を遥かに超える2,000名以上の応募があり、収容できない人たちのために急遽ビデオで視聴できる会場まで用意したとのこと。
これだけでもIoTへの関心が、沸騰していることが分かります。
今回は第一回目の昨年に比べ、出展した企業の数は倍以上に増えています。
会場のあちらこちらで機器のデモンストレーションや、システムのプレゼンテーションが行われ、 多くの来場者が足を止め、熱心に説明に聞き入っていました。
大企業向けの大掛かりで高価なシステムばかりではありません。
従来から使っている古い機器や設備に後付けでセンサーを装着し、そこから得られるデータ―を通信で集約し、 製造ラインの現実の姿を見える化するシステムが数多く展示されています。中小企業にも手が届く、 そこそこの額の投資で工場をスマート化することが可能だと、改めて認識できました。
その他にもAIを駆使し画像処理を高度化するためのソフトや、 AR(拡張現実感)を活用して視線上に様々な情報を投影するスマートグラス(眼鏡)などなど、とても一日では回りきれません。
当社でも日常的に数多くの機器や設備が稼働しています。
そうしたものが何らかの理由で停止することは、積もり積もれば大きな生産ロスにつながります。
IoTの導入で可視化できるから問題点を的確に把握でき、迅速かつ適切な対応が取れるのです。
これから人手の確保が増々難しくなることを考えると、IoTで現在人が直接行っている点検作業を効率化することはもちろんのこと、 機器や設備の異常事態を予測して、トラブルを未然に防ぐ予防保全まで視野に入ってきます。
当社にとって工場のスマート化は夢の世界の話ではなく、目の前の課題を克服するための、極めて現実的な取り組みなのだと理解できました。
七島 徹
2018.01.11
柏洋通信Vol.61
【二本松市の賀詞交歓会に出席しました。】(1/11)
多くの会社で仕事始めとなった1月5日、二本松市では恒例の賀詞交歓会が開催され、私も出席しました。
今年も二本松商工会議所とあだたら商工会との共催です。
国会議員や県会議員のご来賓も含め総勢300名近くが集まり、新春にふさわしい華やかな会となりました。
冒頭、二本松商工会議所の会頭と二本松市長のご挨拶では、景気は穏やかに持ち直してはいるものの、 まだまだ地方や中小企業までには至っておらず、人口減少はさらに地方を疲弊させること、また福島県は農産物を中心に、 今も東日本大震災の風評被害が続く厳しい状況に触れられました。
こうしたお話を聞くにつけ、今年も決して楽観できない現実を改めて認識した次第。
未だお屠蘇気分の抜けきれぬ私でしたが、経営者として自身の会社の業績ばかりではなく、 地域の発展にもどのように貢献すべきかを考える、またとない機会になりました。
さて、今年の私の目標は、良きにつけ悪しきにつけ、何事も曖昧にせずに決着をつけることです。
そのためにも「とことん、しつこく、あきらめず」を信条に、今年一年頑張って参る所存です。
そして、今年もまた「柏洋通信」をよろしくお願い致します。
七島 徹
2017.12.14
柏洋通信Vol.60
【「国際画像機器展2017」に行ってきました。】(12/14)
今年も横浜パシフィコで12月6~8日の日程で開催された、「国際画像機器展2017」に行ってきました。
画像機器本体のハード面での発展はもとより、画像そのものの認識技術、 特にディープラーニング(機械学習)を駆使したAI技術の進展が、この手の世界を大きく変えようとしています。
ここ横浜パシフィコを舞台に、画像機器に関する大規模な展示会は年2回行われているのですが、 半年でその内容が大きく変わるとも言われています。
6月に開催された「画像センシング展2017」はスケジュールが合わず、1年ぶりの展示会になりました。
いやがおうにも気持ちが高まります。
さて、今年は「Deep Learning(機械学習)が革新する画像認識」と題するセミナーに参加することができました。
ディープラーニングは正にタイムリーなテーマだけに、会場は多くの人で埋まっていました。
外観検査、異物検査、寸法検査に、人の目の代わりにマシンビジョンを活用することは今や常識です。
カメラや画像認識技術の急速な進化もあって、一定の環境の下、例えば検査対象が同じ製品、 検査対象の面や輪郭をはっきり写すことができる、良・不良の判定基準が明確であり、 個人差が入り込まないでは、かなりの効果が出せるようになっています。
しかしながら実際の製造現場では、このような恵まれた条件は極々まれだと言わざるを得ません。
当社を例にとっても検査の対象物は、小は10ccの化粧びんから大は1ℓのビールびんまで、様々な大きさ、形状の製品が数百種類に及びます。
そもそも対象物そのものがガラスびんですから、光を透過したり反射したりと一筋縄ではいきません。
照明やレンズなど光学的な工夫や、画像処理の技術を駆使しても完璧とはいかず、 どうしても人の目に頼らざるを得ないのが現状です。
当社のみならず、セミナー受講者の熱い視線からも、多くの企業が同様の問題を抱えていることが改めて理解できました。
そこで登場するのがディープラーニングです。
ディープラーニングは機械に人の目と、脳に近い判断能力を持たせます。 世界各地で実証試験が始まっている自動運転技術は、正にこうした最先端技術の集大成なのでしょう。
ここからは専門的な分野に踏み込むので、私自身正確に理解できているわけではありませんが、 クラス分類(画像を一定の基準?ごとに分類する機能)とセグメンテーション(画像の位置と種別を推定する機能)が役立つのだそうです。
これらを駆使した結果、金属板の表面に錆がある、なしを的確に判断できるようになった事例が紹介されました。
錆の色は一定ではなく、しかも汚れとの区別も非常につきにくいものです。
従来の手法ではそこがクリアできませんでした。
今回は誤認識した場合でも、人間が見分けのつかなかった事例ばかりでした。
金属の錆の判定には、ディープラーニングが有効であることが証明されました。
クラス分類とセグメンテーションの手法を活用すれば、画像認識能力は格段に向上します。
例えばある人間を認識する場合、従来は輪郭や色など正面から見た画像から認識していましたが、 現在では多くの人間が映り込んだ街角の画像の中から、しかも斜め後方から見える人物を認識できるまでになっています。
ただし、そうした認識を可能にするためには、膨大な数のサンプル画像が必要なことも事実です。最低でも様々な状況の1万枚を超える画像が必要だとか。
そろえるだけで膨大な時間とコストがかかるため、ディープラーニングが一般に普及しにくい一因にもなっているようです。
とはいえ、コンピュータの進歩も想像を絶するものがあります。
コンピュータが自ら学習し、微妙に異なるサンプル画像を作り出すこともできるようになってきたとのこと。
実在する世界のセレブの顔写真からその特徴を学習し、その上で実在しないセレブの顔写真を大量に作り出した例が紹介されていました。
これには驚かされました。
現実にはないものを創造する能力も持ち始めているとは、AI(人工知能)恐るべしです。
何やら壮大な話になってきましたが、製造現場の検査工程から人が消える日も、そう遠くないと思えるようなりました。
七島 徹